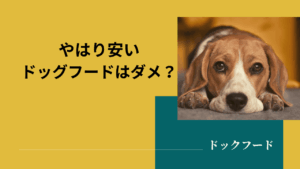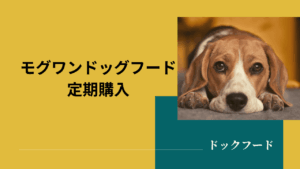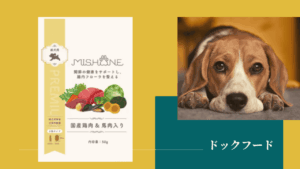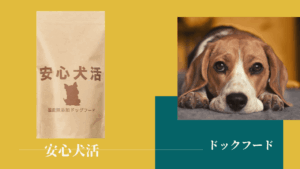愛犬が突然、食べたばかりのドッグフードを未消化のまま吐いてしまうと、飼い主さんとしては非常に心配になりますよね。「何か悪い病気なのでは?」「どう対処すればいいの?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。犬が未消化のドッグフードを吐くという状況には、実は一時的で心配の少ないものから、すぐに対処が必要な病気のサインまで、さまざまな原因が考えられます。この記事では、その原因を一つひとつ解き明かし、ご家庭でできる具体的な対処法、そして動物病院へ連れて行くべきタイミングの見極め方まで、分かりやすく解説していきます。
- 犬が未消化のフードを吐き戻す主な原因
- ご家庭ですぐに実践できる具体的な対処法
- 嘔吐後に冷静に確認すべきポイント
- すぐに動物病院を受診するべき危険なサイン

犬が未消化のドッグフードを吐く主な原因とは
- 早食いや食べ過ぎによる消化不良
- ドッグフードが体質に合わない可能性
- ストレスによる一時的な消化機能の低下
- 食後すぐの運動が吐き戻しにつながる
- 異物の誤飲や病気が隠れているケース
早食いや食べ過ぎによる消化不良
犬が未消化のドッグフードを吐く原因として、最も一般的とも言えるのが「早食い」や「食べ過ぎ」です。特に食欲旺盛な犬や、多頭飼いの環境で他の犬と競い合うように食べる犬によく見られます。
結論として、一度に大量のフードを勢いよく飲み込むと、胃がその急激な量に対応しきれず、消化が始まる前に吐き出してしまうのです。これは、胃の内容物が食道から逆流する「吐出(としゅつ)」と呼ばれる現象に近い場合もあります。
その理由は、固形のドッグフードが十分に噛み砕かれないまま胃に送られると、消化酵素がうまく作用せず、胃に大きな負担がかかるためです。また、急いで食べることでフードと一緒に大量の空気を飲み込んでしまい、胃が膨れて吐き気を催すこともあります。
早食いや食べ過ぎへの対策
ご家庭でできる具体的な対策としては、早食い防止用の凹凸がついた食器を使用する方法が非常に効果的です。物理的に食べるスピードを遅くすることで、しっかり噛むことを促し、空気の飲み込みも減らすことができます。また、1日の食事量を2回に分けている場合は、同じ総量のまま3〜4回に小分けにして与えることで、一度に胃に入る量を減らし、消化の負担を軽減できます。
このように、食事の与え方を少し工夫するだけで、早食いや食べ過ぎによる嘔吐は改善されるケースが多いです。ただし、これらの対策を行っても嘔吐を繰り返す場合は、他の原因を考える必要があります。
ドッグフードが体質に合わない可能性
毎日与えているドッグフードが、実は愛犬の体質に合っていないという可能性も考えられます。フードが体に合わない場合、消化器系がうまく機能せず、未消化のまま吐き出してしまうことがあります。
フードが合わない原因は主に2つあります。一つは、フードに含まれる特定の原材料に対するアレルギーや不耐性です。例えば、穀物(グレイン)や特定の肉類(牛肉、鶏肉など)がアレルゲンとなり、消化器に炎症を起こして嘔吐につながることがあります。もう一つは、フードの脂質が高すぎたり、品質の低い原材料が使われていたりして、犬の消化能力を超えてしまっているケースです。
具体的なサインとしては、嘔吐の他にも、便が緩くなる(下痢)、体を頻繁にかく、皮膚に赤みが出る、耳を気にするなどの症状が見られることがあります。もし新しいフードに切り替えた直後から嘔吐が始まったのであれば、そのフードが原因である可能性は高いでしょう。
フードを切り替える際の注意点
フードを新しいものに切り替える際は、一気に変えるのではなく、最低でも1週間から10日ほどかけて、徐々に新しいフードの割合を増やしていくことが重要です。急な変更は胃腸に大きな負担をかけ、かえって嘔吐や下痢を引き起こす原因となります。愛犬の様子を注意深く観察しながら、ゆっくりと移行させてあげましょう。
もし特定のフードで嘔吐が続くようであれば、アレルギー対応のフードや消化器サポートを目的とした療法食などを獣医師に相談してみるのも一つの方法です。

ストレスによる一時的な消化機能の低下
犬は非常に繊細な動物であり、精神的なストレスが原因で消化機能が乱れ、嘔吐を引き起こすことがあります。人間も緊張するとお腹が痛くなることがあるように、犬もストレスを感じると自律神経のバランスが崩れ、胃腸の働きが鈍くなってしまうのです。
ストレスの原因は多岐にわたります。例えば、以下のようなものが考えられます。
- 引っ越しや部屋の模様替えなどの環境の変化
- 新しい家族やペットが増えた
- 飼い主の留守番時間が長くなった
- 雷や工事の音などの大きな騒音
- 来客が多い
これらのストレスがかかると、胃酸の分泌が過剰になったり、逆に胃の動きが停止してしまったりして、食べたものをうまく消化できなくなります。その結果、食後しばらく経ってから未消化のフードを吐いてしまうことがあります。
普段から神経質な性格の犬や、環境の変化に敏感な犬は特にストレスの影響を受けやすい傾向があります。「最近、吐くことが増えたな」と感じたら、愛犬の生活環境に何か変化がなかったか、ストレスの原因となりうる出来事がなかったかを振り返ってみることが大切です。
対策としては、まず愛犬が安心して過ごせる静かな場所(クレートやベッドなど)を確保してあげましょう。また、散歩や遊びの時間を増やして飼い主とのコミュニケーションを密にし、ストレスを発散させてあげることも重要です。環境の変化に慣れるまでは、できるだけ普段通りの生活リズムを保ってあげるよう心がけてください。
食後すぐの運動が吐き戻しにつながる
食後すぐに走り回ったり、激しく遊んだりすることも、未消化のフードを吐く原因の一つです。これは特に、元気いっぱいの子犬や若い犬によく見られます。
結論から言うと、食後すぐの運動は物理的に胃を揺さぶり、内容物の逆流を誘発します。食べたばかりのフードはまだ胃の中で固形のまま留まっており、消化も始まっていません。その状態で体が激しく動くと、胃が正常な消化活動を行えず、食べたものをそのまま吐き出してしまうのです。
食後は安静に過ごさせましょう
これを防ぐための対策は非常にシンプルで、食後は最低でも30分〜1時間程度は安静にさせることです。散歩や遊びは、食事の前か、食後十分に時間を空けてから行うようにしましょう。特に、胃がねじれてしまう命に関わる病気「胃捻転」のリスクが高い大型犬は、食後の安静が非常に重要になります。
もし愛犬が食後に興奮しやすいタイプであれば、食事の後はクレートやサークルで落ち着かせる習慣をつけるのも良い方法です。穏やかな休息時間を確保することで、消化を助け、嘔吐のリスクを減らすことができます。
異物の誤飲や病気が隠れているケース
これまで挙げてきた原因は比較的対処しやすいものですが、中には注意が必要な「危険な嘔吐」もあります。それが、異物の誤飲や、消化器系の病気が原因となっているケースです。
異物の誤飲
犬はおもちゃの破片、布、ビニール、石、植物など、食べ物以外のものを誤って飲み込んでしまうことがあります。飲み込んだ異物が胃や腸に詰まる(腸閉塞)と、食べたものが先に進めなくなり、激しい嘔吐を繰り返すことがあります。元気がない、食欲がない、お腹を痛がるなどの症状を伴う場合は特に危険なサインです。
注意すべき病気
嘔吐は、さまざまな病気の症状として現れます。特に注意したいのは以下のような病気です。
- 胃腸炎:ウイルスや細菌感染、食事などが原因で胃腸に炎症が起こる。
- 膵炎:膵臓の炎症により消化酵素がうまく働かず、激しい嘔吐や腹痛を引き起こす。
- 腎臓病や肝臓病:体内の毒素を排出できなくなり、吐き気を催す。
- 腫瘍:消化器に腫瘍ができることで物理的に通過障害が起こる。
危険なサインを見逃さないで
もし愛犬が、何度も繰り返し吐く、ぐったりして元気がない、下痢や血便を伴う、水を飲んでも吐いてしまうといった様子を見せる場合は、単なる消化不良ではありません。命に関わる可能性もあるため、様子見をせずに直ちに動物病院を受診してください。
家庭での判断は非常に難しいため、「いつもと違う」「何かおかしい」と感じたら、迷わず専門家である獣医師に相談することが最も重要です。
犬が未消化のドッグフードを吐く場合の対処法
- まずは吐いた物の色や状態を確認する
- 吐いた後の水分補給は慎重に少しずつ
- 食事の回数や量、与え方を見直す
- 吐いた後も元気がない場合は要注意
- 繰り返し吐くなど病院へ行くべき症状
- 総括:犬が未消化のドッグフードを吐く時

まずは吐いた物の色や状態を確認する
愛犬が吐いてしまった時、飼い主さんは慌ててしまうと思いますが、まず冷静に行うべきことは「吐いた物(吐瀉物)の状態をしっかり確認すること」です。吐瀉物の色や内容物は、その原因を探るための重要な手がかりとなります。
確認すべきポイントは、形、色、異物の有無です。ドッグフードの形がそのまま残っていれば、食後すぐに吐いた「吐出」の可能性が高いです。一方、ドロドロに溶けていれば、胃である程度消化が進んだ後の「嘔吐」と考えられます。
特に重要なのが「色」です。以下の表を参考に、吐瀉物の状態を記録しておき、動物病院を受診する際に獣医師に伝えられるようにしておきましょう。
| 吐瀉物の色 | 考えられる主な原因 | 注意点 |
|---|---|---|
| 透明・白い泡 | 胃液、唾液 | 空腹時や水の飲み過ぎで吐くことが多い。一度きりなら心配は少ない。 |
| 黄色い液体・泡 | 胆汁 | 空腹時間が長すぎると胆汁が胃に逆流して吐くことがある(胆汁嘔吐症候群)。 |
| 茶色 | 消化途中のフード、血液 | フードの色に近い場合は心配ないが、コーヒーかすのような黒っぽい茶色は消化管からの出血の可能性があり危険。 |
| 緑色 | 胆汁、植物 | 胆汁が多く混ざったり、異物(草など)を消化しようとしたりすると緑色になることがある。腸閉塞のサインの場合も。 |
| 赤色・ピンク色 | 血液 | 口の中、食道、胃などからの新鮮な出血が疑われる。緊急性が非常に高いため、すぐに動物病院へ。 |
吐瀉物を片付ける前に、スマートフォンなどで写真を撮っておくと、獣医師に状況を正確に伝えるのに非常に役立ちます。また、おもちゃの破片や植物など、フード以外の異物が混じっていないかもしっかり確認してください。
吐いた後の水分補給は慎重に少しずつ
犬が吐いた直後は、脱水症状を心配してすぐに水を与えたくなりますが、ここは少し慎重になる必要があります。なぜなら、吐き気が残っている状態で一度にたくさんの水を与えると、それが刺激となって再び嘔吐を誘発してしまう可能性があるからです。
まずは、嘔吐後30分〜1時間ほどは水や食事を与えるのをやめて、胃腸を休ませてあげましょう。犬が落ち着き、吐き気が収まったように見えたら、水分補給を開始します。
正しい水分補給の手順
- 少量の水から始める:まずスプーン1杯程度のごく少量の水を与えます。
- 様子を見る:水を飲んでから15〜30分ほど様子を見て、吐き戻さないかを確認します。
- 問題なければ徐々に増やす:吐き戻しがなければ、少しずつ水の量を増やしていきます。
この手順を踏むことで、胃腸への負担を最小限に抑えながら水分を補給することができます。常温の水が望ましいですが、もし犬が水を飲みたがらない場合は、氷を数個なめさせたり、肉のゆで汁(味付けなし)の匂いで興味を引いたりするのも一つの方法です。
もし、少量の水を与えても吐いてしまう状況が続くようであれば、脱水が進む危険性が高まります。その場合は家庭での対処は困難なため、速やかに動物病院を受診し、点滴などの処置をしてもらう必要があります。
食事の回数や量、与え方を見直す
嘔吐の原因が病気ではなく、早食いや消化不良といった食事に関連するものである場合、食事の与え方を見直すことで大幅に改善することが期待できます。
最も効果的な方法の一つが、「食事の回数を増やし、1回の量を減らす」ことです。例えば、これまで1日2回で与えていたフードを、同じ1日分の総量を3〜4回に分けて与えるようにします。これにより、一度に胃に入るフードの量が減るため、胃腸への負担が軽くなり、消化がスムーズに進みます。
フードをふやかすのも効果的
ドライフードをぬるま湯でふやかしてから与えるのも、消化を助ける良い方法です。ふやかしたフードは柔らかく、胃での分解が早まります。また、フードの香りが立つため、食欲が落ちている犬の食欲増進にもつながります。
ただし、ふやかしたフードは傷みやすいため、作り置きはせず、食事の都度作るようにしてください。
前述の通り、早食いが原因の場合は、早食い防止用の食器の導入が非常に有効です。食器の内部にある凹凸が障害物となり、犬は時間をかけて少しずつしか食べられなくなります。これにより、よく噛んで食べる習慣がつき、空気の飲み込みも減るため、吐き戻しのリスクを大きく下げることができます。
これらの対策は、特別な病気がない犬の「吐きグセ」を改善するための基本的なアプローチです。愛犬の食事の様子をよく観察し、その子に合った方法を試してみてください。
吐いた後も元気がない場合は要注意
犬が吐いた後の様子を観察することは、その嘔吐の深刻度を判断する上で非常に重要です。一度吐いただけでも、その後ケロッとして普段通り元気に走り回っているのであれば、一時的な問題である可能性が高く、少し様子を見ても良いでしょう。
しかし、吐いた後にぐったりしている、飼い主が呼んでも反応が鈍い、部屋の隅でじっと動かないなど、明らかに元気がない場合は注意が必要です。元気の消失は、体が発している重要なSOSサインであり、単なる食べ過ぎや早食いでは片付けられない問題が隠れている可能性があります。

元気がない時に伴う危険な症状
以下のような症状が嘔吐と同時に見られる場合は、特に注意が必要です。
- 下痢:特に血が混じった下痢(血便)は危険です。
- 震え:腹痛や発熱、低血糖などを示している可能性があります。
- 食欲不振:水を飲もうとしない、好物を見せても食べない。
- 呼吸が荒い:苦痛を感じているサインかもしれません。
犬は不調を言葉で伝えることができません。「元気がない」という状態は、痛みや苦しみを我慢していることの表れです。普段の愛犬の様子を一番よく知っているのは飼い主さんです。「いつもと何か違う」と感じたら、その直感を信じて、迷わず獣医師の診察を受けることを強くお勧めします。
繰り返し吐くなど病院へ行くべき症状
愛犬の嘔吐に際し、飼い主さんが最も迷うのが「動物病院へ行くべきか、もう少し様子を見るべきか」という判断だと思います。ここでは、すぐに獣医師に相談すべき具体的な症状をまとめます。
すぐに動物病院を受診すべきサイン
以下のいずれかの項目に当てはまる場合は、自己判断で様子を見ずに、できるだけ早く動物病院を受診してください。
- 1日に何度も繰り返し吐いている
- 嘔吐が2日以上続いている
- 吐いた物に血液(赤、ピンク、黒っぽい茶色)が混じっている
- 異物を飲み込んだ可能性がある、または吐瀉物に異物が混じっていた
- 嘔吐だけでなく、下痢や震え、発熱などの他の症状も出ている
- ぐったりしていて元気や食欲が全くない
- 水を飲んでもすぐに吐いてしまう
- お腹が張っている、または触ると痛がる様子を見せる
特に子犬や高齢犬、持病のある犬は、体力がないため症状が悪化しやすい傾向にあります。嘔吐による脱水は急速に進むことがあるため、上記のような症状が見られた場合は、ためらわずに受診することが愛犬の命を守ることにつながります。
受診の際に獣医師に伝えること
動物病院へ行く際は、以下の情報を整理しておくと診察がスムーズに進みます。
- いつから吐いているか
- 1日に何回吐いたか
- 吐いた物の写真や実物(可能であれば)
- 食事内容や、いつもと違うものを食べたか
- 嘔吐以外の症状(元気、食欲、便の状態など)
- 持病や服用中の薬の有無
的確な情報が、迅速で正確な診断の手助けとなります。
総括:犬が未消化のドッグフードを吐く時
- 犬が未消化のフードを吐く最も多い原因は早食いや食べ過ぎ
- フードが体質に合わずアレルギーや消化不良を起こしている可能性もある
- 環境の変化などによる精神的ストレスも嘔吐の一因となる
- 食後すぐの激しい運動は物理的に嘔吐を誘発する
- 吐いた後はまず落ち着いて吐瀉物の色や内容物を確認する
- 吐瀉物の写真は診断の助けになるため撮っておくと良い
- 吐いた直後の水分補給は避け、時間を置いてから少量ずつ与える
- 早食い防止食器や食事の回数を増やす工夫が効果的
- フードをぬるま湯でふやかすと消化の負担を軽減できる
- 一度吐いても元気で食欲があれば、少し様子を見ても良い場合が多い
- 吐いた後にぐったりしている場合は危険なサインの可能性
- 何度も繰り返し吐く、血が混じる場合はすぐに病院へ
- 下痢や震えなど他の症状を伴う場合も速やかに受診が必要
- 異物の誤飲が疑われる場合は命に関わるため緊急性が高い
- 「いつもと違う」という飼い主の直感は大切にし、迷ったら獣医師に相談する