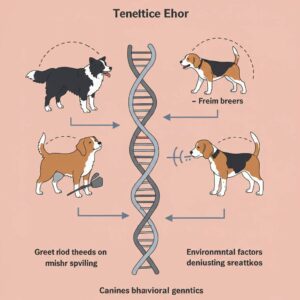新しい家族としてワンちゃんを迎えようと考えたとき、犬をブリーダーから買うという選択肢が頭に浮かぶ方は多いでしょう。しかし、実際に検討し始めると、ブリーダーから犬を飼う値段の相場や、具体的なブリーダーから買う流れなど、分からないことばかりかもしれません。また、ブリーダーから買う際の犬の注意点や、万が一ブリーダーの犬に売れ残りがいた場合はどうなるのかといった不安を感じることもあると思います。この記事では、ブリーダーからワンちゃんを迎える際のメリット・デメリットから、信頼できるブリーダーの見分け方まで、あなたの疑問や不安を解消するための情報を網羅的に解説していきます。
- ブリーダーとペットショップの具体的な違い
- ブリーダーから犬を迎える際の費用や流れ
- 信頼できるブリーダーを見分けるための重要ポイント
- 購入前に知っておくべき注意点や確認事項
犬をブリーダーから買うメリットとデメリット
- 専門家から直接アドバイスをもらえる
- 手厚いアフターフォローが受けられる
- ペットショップとの違いを徹底比較
- ブリーダーから犬を飼う値段の内訳とは
- 親犬や兄弟犬に会えることの重要性
- ブリーダーの犬に売れ残りは存在する?
専門家から直接アドバイスをもらえる

ブリーダーから犬を迎える最大のメリットの一つは、犬種の専門家から直接、詳細なアドバイスを受けられることです。多くのブリーダーは特定の犬種に特化しており、その犬種の歴史や気質、遺伝的な傾向、かかりやすい病気など、深い知識と豊富な経験を持っています。
ペットショップでは様々な犬種を扱っているため、一つの犬種に対する情報が限定的になる場合があります。しかし、ブリーダーであれば、あなたが迎えようとしている子犬の性格はもちろん、その両親や祖父母の性格、健康状態まで把握していることがほとんどです。これにより、子犬が将来どのような姿や性格に成長するのか、ある程度予測しながら迎える準備ができます。
「この子は少し臆病なところがあるけど、慣れるとすごく甘えん坊ですよ」「お父さん犬がボール遊びが大好きだったので、この子も活発に遊ぶのが好きかもしれません」といった、その子ならではの具体的な情報を教えてもらえるのは、ブリーダーならではの魅力ですね。
また、飼育に関する疑問や不安、例えば「この犬種に合ったフードは?」「しつけで気をつけるべきポイントは?」といった質問にも、その場で的確に答えてもらえます。専門家と直接対話できる安心感は、特に初めて犬を飼う方にとって、何物にも代えがたいメリットと言えるでしょう。
手厚いアフターフォローが受けられる

犬を迎えた後の手厚いアフターフォローも、ブリーダーを利用する大きな魅力です。犬との生活は、迎えたその日からが本当のスタートであり、日々の成長の中で様々な疑問や問題に直面することがあります。
例えば、子犬が急にご飯を食べなくなったり、夜鳴きが続いたり、トイレを失敗したりといった時、初心者にとってはパニックになってしまうかもしれません。そんな時、その子犬を育てたブリーダーに直接相談できるのは、非常に心強いサポートです。
多くの優良なブリーダーは、自分が育てた子犬たちが新しい家庭で幸せに暮らすことを心から願っています。そのため、お迎え後も連絡を取り合い、しつけの悩みや健康に関する相談に親身に乗ってくれるケースが少なくありません。言ってしまえば、ブリーダーは愛犬にとって「生みの親」のような存在。誰よりもその子のことを理解している専門家が、いつでも味方でいてくれるという安心感は、ペットライフをより豊かなものにしてくれます。
生涯にわたるお付き合いも
ブリーダーによっては、年に一度、その犬舎で生まれた犬たちが集まる「里帰り会」のようなイベントを開催するところもあります。兄弟犬との再会や、他の飼い主さんとの情報交換など、ブリーダーを介したコミュニティが形成されることも、魅力的なポイントです。
ペットショップとの違いを徹底比較
犬を迎える際、多くの人がブリーダーとペットショップで悩みます。どちらにもメリット・デメリットがありますが、ここではいくつかの重要な観点から両者の違いを比較してみましょう。
このように、どちらが良いと一概に言えるものではなく、何を重視するかによって選択は変わってきます。それぞれの特徴を正しく理解した上で、ご自身のライフスタイルや考え方に合った選択をすることが大切です。
| 比較項目 | ブリーダー | ペットショップ |
|---|---|---|
| 専門性 | 特定の犬種に特化しており、知識が深い | 多犬種を扱うため、知識は広範だが浅い傾向 |
| 親犬の確認 | 多くの場合、親犬や兄弟犬に会える | 基本的に会うことはできない |
| 飼育環境 | 直接犬舎を見学し、生育環境を確認できる | どのような環境で育ったか不明な場合が多い |
| 流通 | 流通を経ないため、子犬への負担が少ない | オークション等を経由し、移動によるストレスがある |
| 健康リスク | 感染症リスクは比較的低い傾向 | 複数の動物が集まるため、感染症リスクは高まる傾向 |
| アフターフォロー | 飼育相談など、手厚いサポートが期待できる | 店舗やスタッフによる差が大きい |
| 価格 | 仲介料がなく割安な場合もあれば、血統により高額な場合もある | 人件費や仲介料が上乗せされる傾向 |
ブリーダーから犬を飼う値段の内訳とは
ブリーダーから犬を迎える際、表示されている「生体価格」だけで判断してはいけません。実際には、その他にもいくつかの費用が必要になることがほとんどです。後から「思っていたより高かった」と慌てないためにも、値段の内訳をしっかり理解しておきましょう。
主に、生体価格に加えて以下の費用が発生するのが一般的です。
1. ワクチン接種費用
子犬は感染症から身を守るために、複数回のワクチン接種が必要です。ブリーダーの元で少なくとも1回、多い場合は2回のワクチン接種を終えていることが多く、その実費が請求されます。1回あたり5,000円から10,000円程度が目安です。
2. マイクロチップ装着・登録費用
2022年6月から、ブリーダーやペットショップで販売される犬猫にはマイクロチップの装着が義務化されました。ブリーダーが装着まで済ませている場合、その費用(数千円程度)と、飼い主情報を登録するための費用(1,000円程度)が必要になります。
3. 健康診断費用
お迎え前に、提携する動物病院で健康診断を行っているブリーダーもいます。その際の実費が上乗せされることがあります。
総額で考えることが重要
例えば、生体価格が30万円のチワワの場合、ワクチン2回分(約15,000円)とマイクロチップ関連費用(約5,000円)が加わり、合計で32万円程度がお迎え時の支払額になるといったイメージです。ブリーダーによって含まれる内容や金額は異なるため、契約前に必ず総額と内訳を確認しましょう。
ペットショップではこれらの諸費用に加えて、独自の保証パックなどでさらに10万円〜20万円ほど上乗せされるケースも見られます。この点が、ブリーダーの方が合計金額は安くなることが多いと言われる理由の一つです。
親犬や兄弟犬に会えることの重要性
ブリーダーから犬を迎える大きなメリットとして、親犬や兄弟犬に会える可能性が高いことが挙げられます。これは、単に「かわいい姿を見られる」というだけでなく、子犬選びにおいて非常に重要な意味を持ちます。
なぜなら、子犬の将来の姿や性格は、遺伝的要因に大きく影響されるからです。特に以下の2つの点を予測する上で、親犬の情報は貴重な手がかりとなります。

1. 成長後のサイズや容姿
「この子はティーカップサイズになりますか?」といった質問はよく聞かれますが、子犬の段階で将来の大きさを正確に予測することは困難です。しかし、実際に両親犬を見れば、その子犬が成犬になったときのおおよそのサイズ感や毛色、骨格などをイメージしやすくなります。
2. 性格や気質

犬の性格は、社会化期の経験だけでなく、親から受け継ぐ気質も大きく関係します。穏やかで人懐っこい両親から生まれた子犬は、同様の性質を持つ可能性が高いと言えます。逆に、過度に臆病だったり、攻撃的だったりする親犬を見てしまうと、その子犬を迎えるかどうかを慎重に考えるきっかけにもなります。
必ず会えるわけではない
ただし、全てのブリーダーで必ず親犬に会えるとは限りません。父犬が他の犬舎にいる場合や、母犬が出産後の体調を考慮して見学を制限している場合もあります。また、衛生管理の観点から犬舎の一部しか見学できないこともあります。親犬との対面を強く希望する場合は、問い合わせの段階で可能かどうかを確認しておくことをお勧めします。
ブリーダーの犬に売れ残りは存在する?

「ブリーダー 犬 売れ残り」と検索すると、少しネガティブな印象を受けるかもしれません。しかし、この「売れ残り」という言葉の捉え方には注意が必要です。
ペットショップでは生後3ヶ月を過ぎると価格が下がる傾向にあるため、「月齢が進んだ子=売れ残り」というイメージがつきがちです。しかし、ブリーダーの世界では少し事情が異なります。
優良なブリーダーの中には、子犬の社会化を重視し、あえて生後3ヶ月以降まで親犬や兄弟犬と一緒に過ごさせる方針をとる人もいます。この期間に犬社会のルールを学ぶことで、問題行動が少なく、精神的に安定した犬に育ちやすいと考えられているからです。
また、ドッグショーへの出場を目指すブリーダーが、将来有望な子を手元に残していたものの、成長過程でショータイプの基準から少し外れたために、一般家庭向けのペットとして新しい家族を探すケースもあります。このような子は、骨格がしっかりしており、健康状態も良好な場合が多いです。
つまり、ブリーダーの元にいる月齢が進んだ子は、必ずしも「人気がなくて売れ残った」わけではないのです。むしろ、以下のようなメリットがあります。
- 基本的なトイレトレーニングやしつけが済んでいることがある
- 性格や個性がはっきりしてきているため、相性を見極めやすい
- ワクチンプログラムが完了しており、すぐにお散歩デビューできる
- 体力がついており、初めて犬を飼う人でも体調管理がしやすい
もちろん、中には単純に買い手が見つからなかったケースも存在します。月齢が進んでいる理由については、ブリーダーに直接率直に質問してみることが大切です。「なぜこの子はまだここにいるのですか?」という問いに、誠実に答えてくれるかどうかも、ブリーダーを見極める一つの指標になるでしょう。
失敗しないために犬をブリーダーから買う方法
- 信頼できるブリーダーの見分け方を解説
- ブリーダーから買う流れと具体的な手順
- 犬舎見学で確認すべきポイントとマナー
- ブリーダーから買う注意点と犬の健康状態
- 血統で確認すべき近親交配のリスク
- 自分に合った犬をブリーダーから買うには
信頼できるブリーダーの見分け方を解説
残念ながら、ブリーダーの中には利益優先で犬の健康や福祉を軽視する「悪質ブリーダー」も存在します。大切な家族を迎える上で失敗しないためには、信頼できる優良なブリーダーを見分ける目が不可欠です。ここでは、そのための具体的なチェックポイントを解説します。
1. 動物取扱業の登録を確認する
日本で犬の繁殖・販売を行うには、「第一種動物取扱業者」としての登録が法律で義務付けられています。公式サイトや犬舎に登録番号が明記されているか、必ず確認しましょう。これは最低限の条件です。
2. 犬舎や飼育環境が清潔に保たれているか
犬舎見学の際には、施設全体の清潔さをチェックします。排泄物が放置されていたり、強い悪臭がしたりする環境は論外です。犬たちが過ごすスペースが、衛生的で快適な空間に保たれているかは非常に重要なポイントです。
3. 親犬や他の犬たちの健康状態と様子
子犬だけでなく、犬舎にいる他の犬たち(特に親犬)の様子も観察しましょう。毛艶は良いか、痩せすぎていないか、皮膚病などの兆候はないか、そして人に対して怯えたり攻撃的になったりせず、穏やかな表情をしているかなどを確認します。犬たちへの愛情は、その姿に表れます。
4. 質問に対して誠実かつ丁寧に答えてくれるか
こちらからの質問に対して、専門的な知識に基づいて、誠実に答えてくれるかは信頼性を見極める上で最も重要です。良い面だけでなく、その犬種の遺伝的好発疾患(かかりやすい病気)などのデメリットについても、包み隠さず説明してくれるブリーダーは信頼できます。逆に、質問をはぐらかしたり、面倒くさそうな態度をとったりするブリーダーは避けるべきです。
こんなブリーダーは要注意!
- 犬舎の見学を頑なに拒否する
- 親犬を見せてくれない(正当な理由なく)
- 契約を急かしたり、衝動買いを煽ったりする
- 遺伝子検査の結果など、健康に関する情報を開示しない
- 子犬の受け渡し場所を、犬舎以外の駐車場や駅などに指定する
これらのポイントを総合的に判断し、心から信頼できると感じるブリーダーから、大切な家族を迎えましょう。
ブリーダーから買う流れと具体的な手順
ブリーダーから犬を迎えたいと思っても、具体的にどうすればよいか分からない方も多いでしょう。ここでは、一般的な問い合わせからお迎えまでの流れを、4つのステップに分けて解説します。
ステップ1:子犬を探し、ブリーダーに問い合わせる
まずは、ブリーダー紹介サイトや、ブリーダー個人のウェブサイトなどで、希望の犬種や条件に合う子犬を探します。気になる子が見つかったら、サイトの問い合わせフォームや電話でブリーダーに連絡を取ります。このとき、家族構成や飼育経験、住環境などを伝えておくと、話がスムーズに進みます。
ステップ2:犬舎見学の日時を予約する
問い合わせ後、ブリーダーとやり取りをして犬舎見学の日程を調整します。ブリーダーは店舗ではなく、多くの場合個人宅も兼ねています。アポイントなしで訪問するのは絶対にやめましょう。購入意思がある程度固まった上で、見学を申し込むのがマナーです。
ステップ3:犬舎を見学し、契約を決める
予約した日時に犬舎を訪問します。子犬の健康状態や性格、ブリーダーの人柄、飼育環境などを自分の目でしっかりと確認しましょう。疑問点は全て質問し、納得できたら契約手続きに進みます。契約書の内容をよく読み、支払い方法や引き渡しの日時、場所などを決めます。
ステップ4:準備を整え、子犬をお迎えする

契約で決めた引き渡し日までに、子犬を迎えるための準備(ケージ、トイレ、フードなど)を完璧に整えておきます。そして、いよいよお迎え当日。ブリーダーから、子犬が食べていたフードや飼育に関する最終的な注意点などの説明を受け、新しい家族を自宅へ連れて帰ります。
これが一般的な流れですが、ブリーダーの方針によって詳細は異なります。お迎えまでの期間、子犬の成長の様子を写真や動画で送ってくれるブリーダーも多く、待っている時間も楽しむことができますよ。
犬舎見学で確認すべきポイントとマナー
犬舎見学は、子犬とブリーダーを直接知るための非常に重要な機会です。しかし、そこは子犬たちが生活するデリケートな場所。お互いが気持ちよく過ごすために、守るべきマナーと確認すべきポイントがあります。
犬舎見学の基本マナー
- 事前予約は必須:前述の通り、アポイントなしの訪問は厳禁です。必ず事前に連絡し、日時を約束しましょう。
- 見学は1日1件に:感染症予防のため、複数の犬舎やペットショップを同日にハシゴするのは絶対に避けてください。ワクチン未接種の子犬にとって、外部からのウイルスは命取りになりかねません。
- 清潔な服装で訪問する:他の動物の匂いや菌を持ち込まないよう、清潔な服装と靴で伺いましょう。
- むやみに犬を触らない:ブリーダーの許可なく、子犬や他の犬に触れるのはマナー違反です。まずはブリーダーの指示に従いましょう。
- 購入意思を持って見学する:「ただ見てみたい」という興味本位の見学は避けましょう。ブリーダーの貴重な時間をいただくという意識を持つことが大切です。
見学時に確認すべきチェックポイント
見学では、以下の点を自分の目でしっかり確認しましょう。
| チェック項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 子犬の様子 | 元気で活発か、目やにや鼻水はないか、毛艶は良いか、歩き方に異常はないかなどを観察します。 |
| 親犬・兄弟犬 | 可能であれば対面させてもらい、性格や健康状態、子犬との関係性を確認します。 |
| 飼育環境 | 犬舎全体が清潔か、適切な温度・湿度が保たれているか、十分な運動スペースがあるかなどをチェックします。 |
| ブリーダーの人柄 | 質問に誠実に答えてくれるか、犬たちへの愛情が感じられるか、デメリットも話してくれるかなど、信頼性を判断します。 |
これらのマナーとポイントを押さえて、有意義な犬舎見学にしてください。
ブリーダーから買う注意点と犬の健康状態
ブリーダーから犬を迎えることは多くのメリットがありますが、注意すべき点も存在します。特に、子犬の健康状態を見極めることは、後々の幸せなペットライフの根幹に関わる重要な要素です。
最大の注意点は、やはり「悪質なブリーダー」の存在です。彼らのもとでは、非衛生的な環境で乱雑な繁殖が繰り返され、遺伝的疾患や感染症を持つ子犬が生まれるリスクが高まります。ブリーダーだから安心、と無条件に信じるのは危険です。
流通しないことのデメリット
ペットショップの場合、オークションなどで獣医師やバイヤーといった第三者のチェックが入る機会があります。しかし、ブリーダーからの直接購入では、基本的に第三者の介入がありません。そのため、もしブリーダーが意図的に子犬の健康問題を隠していた場合、初心者がそれを見抜くのは非常に困難です。だからこそ、飼い主自身が知識をつけ、信頼できるブリーダーを慎重に選ぶ必要があります。
特に、以下の感染症は子犬にとって致命的となる可能性があり、注意が必要です。
- パルボウイルス感染症:致死率が非常に高く、激しい嘔吐や下痢を引き起こします。潜伏期間があるため、お迎え時に元気そうに見えても安心はできません。
- ジステンパーウイルス感染症:こちらも致死率が高く、神経症状など様々な症状を示します。
これらの感染症リスクは、ブリーダーの元での適切なワクチン接種と衛生管理によって大幅に低減できます。ワクチン証明書の確認はもちろん、親犬や犬舎全体の健康管理について、ブリーダーに詳しく質問することが重要です。
血統で確認すべき近親交配のリスク
純血種の犬を迎える上で、「血統書」は重要な書類ですが、その見方や意味を正しく理解している人は少ないかもしれません。血統書を読み解く上で、特に注意したいのが「近親交配」のリスクです。
犬の世界では、犬種のスタンダード(理想像)に近い、優れた形質を固定するために、ある程度の近親交配(ラインブリーディング)が行われることがあります。これは、特定の良い特徴を色濃く受け継がせるための伝統的な手法の一つです。
しかし、これを過度に行うと「インブリーディング(極近親交配)」となり、様々な問題が生じるリスクが高まります。
近親交配のデメリット
- 遺伝的多様性の喪失:血が濃くなりすぎると、遺伝子のバリエーションが失われます。
- 近交弱勢:繁殖能力の低下、虚弱体質、子犬の死亡率の上昇、寿命の短縮などが起こりやすくなります。
- 遺伝性疾患の発現:両親が共に持っている特定の病気の遺伝子が、子犬で発症する確率が高まります。
血統書を見れば、父母、祖父母、曾祖父母の名前が記載されています。その中に、同じ犬の名前が何度も出てくる場合は、近親交配の程度が強いと考えられます。

全ての近親交配が悪いわけではありませんが、健康な犬を迎えたいと考えるなら、近親交配のリスクについては理解しておくべきです。気になる場合は、ブリーダーに「この子の両親の血縁関係は近いですか?」「遺伝子検査は行っていますか?」と率直に質問してみましょう。誠実なブリーダーであれば、交配の意図や遺伝的リスクについて正直に説明してくれるはずです。
自分に合った犬をブリーダーから買うには
この記事の最後に、ブリーダーから犬を迎えるという選択を成功させるための総まとめとして、後悔しないためのポイントをリスト形式でご紹介します。これまでの情報を踏まえ、あなたとあなたの家族にとって最高のパートナーを見つけるためにお役立てください。
ブリーダーから犬を買うための最終チェックリスト
- ブリーダーは犬種の専門家であり深い知識を持つ
- 迎えた後のしつけや健康相談などアフターフォローが期待できる
- ペットショップとは流通経路や価格構成が根本的に異なる
- 価格は生体代金だけでなくワクチン代などの諸経費も確認する
- 親犬や兄弟犬に会うことで将来の姿や性格を予測しやすくなる
- 月齢の進んだ犬は社会化が進んでいるなどのメリットもある
- 信頼できるブリーダーは動物取扱業の登録が必須である
- 犬舎の清潔さや犬たちの健康状態は必ず自分の目で確認する
- 質問に誠実に答えデメリットも説明してくれるかが重要
- 犬舎見学は感染症予防のため1日1件のマナーを守る
- 悪質なブリーダーを避けるため飼い主も知識を持つ必要がある
- 血統書で過度な近親交配がないかを確認する視点も持つ
- 遺伝性疾患のリスクについて正直に話してくれるかを見極める
- 自分のライフスタイルや住環境に合う犬種か再確認する
- 最終的にはブリーダーの人柄を信じられるかが決め手となる
ブリーダーから犬を迎えることは、素晴らしい出会いの始まりです。十分な情報収集と準備を行い、信頼できるブリーダーと共に、かけがえのない家族との新しい生活をスタートさせてください。