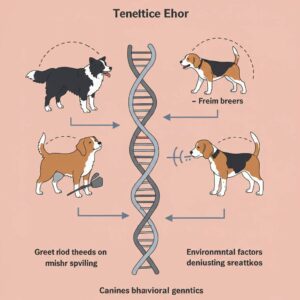子犬や愛犬のうれしょん(嬉ション)にお困りではありませんか?大好きな飼い主さんへの愛情表現だと分かっていても、来客時や外出先で粗相をされると少し困ってしまいますよね。犬のうれしょんはいつまで続くのか、またうれしょんをする犬は何歳までこの行動が見られるのか、多くの飼い主さんが疑問に思う点です。実は、うれしょんは単なるお漏らしではなく、犬の習性や感情が関係しています。この記事では、犬のうれしょんの治し方を含め、その原因から具体的な対策までを分かりやすく解説します。愛犬との暮らしをより快適にするためのヒントがきっと見つかります。
- うれしょんの主な原因と理由
- うれしょんが続く期間の目安
- 具体的なうれしょんの直し方とコツ
- どうしても治らない場合の対処法と注意点
犬のうれしょんはいつまで?主な原因と理由
- うれしょんの理由は興奮と服従心
- うれしょんをしやすい犬の特徴とは
- 子犬の犬のうれしょんはいつまで続く?
- うれしょんする犬は何歳まで続くの?
- 成長と共に落ち着くケースが多い
うれしょんの理由は興奮と服従心
犬がうれしょんをしてしまうのには、大きく分けて2つの理由があると言われています。それは「興奮」と「服従心」です。
まず一つ目の理由は、嬉しい、楽しいといった感情の高ぶりによる「興奮」です。大好きな飼い主さんが帰宅した時や、たくさん褒められた時などにテンションが上がり、自分でも感情をコントロールできなくなってしまうことがあります。このように過度に興奮すると、おしっこを溜めておく役割を持つ膀胱の筋肉(膀胱括約筋)が緩み、意図せずおしっこが漏れてしまうのです。これは獣医学的に「興奮排尿」とも呼ばれます。
そしてもう一つの理由は、相手への「服従心」を示すための行動です。犬の習性として、自分より立場が上の相手に対してお腹を見せたり、おしっこを漏らしたりすることで「あなたに敵意はありません」「私はあなたの下です」という気持ちをアピールすることがあります。これを「服従排尿」と呼び、飼い主さんへの「大好き!」という強い気持ちや敬意の表れと考えることができるのです。
豆知識:うれしょんは愛情の証?
うれしょんは、犬が飼い主さんに対して強い信頼と愛情を抱いている証拠とも言えます。困った行動ではありますが、叱る前にまず「そんなに私のことが好きなんだな」と、愛犬の気持ちを受け止めてあげることが大切です。
うれしょんをしやすい犬の特徴とは
うれしょんはどんな犬にも起こり得ますが、特にしやすいとされる犬にはいくつかの特徴があります。主に「年齢」「体の大きさ」「性格」が関係していると考えられています。
ここでは、うれしょんをしやすい犬の特徴をまとめました。
| 特徴 | うれしょんをしやすい理由 |
|---|---|
| 子犬 | 膀胱の筋肉が未発達で、おしっこのコントロールが難しい。また、感情の抑制も苦手で興奮しやすいため。 |
| 小型犬 | 体が小さいため、自分より大きな存在(人や他の犬)が多く、服従心を示す機会が増える傾向にあるため。 |
| 怖がり・臆病な性格の犬 | 精神的に不安定になりやすく、相手に服従を示すことで安心感を得ようとする。ストレスや恐怖から漏らしてしまうことも。 |
| 飼い主への依存心が強い犬 | 飼い主への「大好き」という気持ちを強くアピールするため、服従排尿をしやすい。 |
もちろん、これらはあくまで傾向であり、個体差が大きいことを理解しておく必要があります。ただ、もしご自身の愛犬がこれらの特徴に当てはまる場合は、うれしょんをしやすいタイプかもしれないと意識しておくと、対策が立てやすくなります。

子犬の犬のうれしょんはいつまで続く?
子犬のうれしょんに悩む飼い主さんは非常に多いですが、そのほとんどは成長過程で見られる一時的なものです。
前述の通り、子犬は膀胱の機能がまだ完全に発達していません。そのため、成犬のように長時間おしっこを我慢することができず、少しの興奮でも漏らしてしまいがちです。また、子犬は好奇心旺盛で感情表現もストレートなため、あらゆる刺激に対して過剰に興奮しやすい時期でもあります。
では、子犬の犬のうれしょんはいつまで続くのでしょうか。これには個体差がありますが、一般的には体の成長が進み、膀胱の筋肉がしっかりしてくる生後6ヶ月〜1歳頃には、自然と頻度が減ってくることが多いと言われています。精神的な成長とともに感情のコントロールも上手になってくるため、焦らずに見守ってあげることが大切です。
うれしょんする犬は何歳まで続くの?
子犬の場合は成長とともに改善されることが多い一方で、「成犬になってもうれしょんが治らない」というケースもあります。では、うれしょんをする犬は何歳までその行動が続く可能性があるのでしょうか。
これに関しては、「何歳まで」という明確な答えはありません。なぜなら、成犬のうれしょんは、体の機能的な問題よりも、その犬が持つ性格や気質、そして飼い主さんとの関係性が大きく影響するためです。例えば、非常に甘えん坊で飼い主さんへの依存心が強い犬や、極度に怖がりな犬は、成犬になっても服従心を示すためにうれしょんを続けることがあります。
成犬のうれしょんは、年齢よりも「個々の性格」と「生活環境」に左右されると覚えておきましょう。そのため、治すためにはその子の性格に合ったアプローチが必要になります。
成長と共に落ち着くケースが多い
ここまで解説してきたように、犬のうれしょんは様々な要因が絡み合っています。特に子犬期に見られるうれしょんは、多くの飼い主さんが経験する「あるある」な悩みの一つです。
しかし、重要なことなので繰り返しますが、ほとんどのケースでは犬が身体的・精神的に成熟するにつれて、自然と落ち着いてきます。膀胱の機能が安定し、社会性を学び、感情のコントロールが上手になることで、うれしょんの頻度は確実に減っていきます。
飼い主さんとしては、床を汚されるなど大変な面もありますが、「これは成長の証なんだ」と少しだけ広い心で捉え、焦らずに見守ってあげてください。もちろん、ただ待つだけでなく、次にご紹介する「直し方のコツ」を実践することで、よりスムーズな改善が期待できます。
犬のうれしょんはいつまでも続く?直し方のコツ
- 犬のうれしょんの治し方で大切なこと
- 興奮させないための飼い主の対応
- 帰宅時や来客時のうれしょん対策
- 叱るのは逆効果!正しい対処法
- オムツやマナーバンドの活用も有効
- どうしても治らない場合は動物病院へ
犬のうれしょんの治し方で大切なこと
犬のうれしょんを改善するために、最も大切で基本的な心構えがあります。それは、「犬を過度に興奮させない」ということです。
うれしょんの引き金となるのは、多くの場合「嬉しい!」「楽しい!」という感情の爆発です。この興奮のスイッチを入れてしまっているのが、実は飼い主さん自身の行動であるケースが少なくありません。愛犬が喜ぶ姿は可愛いものですが、うれしょんを治したいのであれば、まずは飼い主さんが冷静になり、愛犬の興奮をあおらないように努めることが全ての基本となります。
改善の第一歩
うれしょんを治すための最初のステップは、犬が興奮しそうな状況を予測し、その場面で飼い主さんが意識的に冷静な態度を保つことです。犬の感情は、飼い主の感情に大きく影響されることを忘れないでください。
興奮させないための飼い主の対応
では、具体的にどのように対応すれば、犬を興奮させずに済むのでしょうか。ポイントは「構いすぎない」ことです。
例えば、飼い主さんの帰宅時に愛犬が興奮して駆け寄ってきたとします。ここで「ただいまー!」と高い声で応えたり、すぐに撫でたりすると、犬の興奮はピークに達してしまいます。そうではなく、愛犬が落ち着くまではあえて無視するくらいの冷静さが必要です。
具体的には、以下のような対応を心がけてみてください。
- 帰宅してもすぐに犬に声をかけない、目を合わせない。
- 犬が飛びついてきても、静かに体をかわして通り過ぎる。
- 犬の名前を呼んだり、高い声を出したりしない。
- 犬の興奮が収まり、おとなしくなったら、初めて「ただいま」と静かに声をかけてあげる。
これを繰り返すことで、犬は「興奮しても良いことはない」「落ち着けば構ってもらえる」と学習し、次第に自分で感情をコントロールできるようになります。最初はかわいそうに感じるかもしれませんが、愛犬のためだと思って心を鬼にすることも時には重要です。
帰宅時や来客時のうれしょん対策
うれしょんが特に起こりやすいのが「飼い主さんの帰宅時」と「来客時」です。それぞれのシチュエーションに合わせた具体的な対策を知っておきましょう。
飼い主さんの帰宅時
前述の通り、帰宅後はすぐに構わず、愛犬が落ち着くまで待つのが基本です。荷物を置いたり、着替えを済ませたりと、飼い主さんが自分の用事を先に済ませ、その間に犬がクールダウンする時間を作りましょう。
来客時
お客さんが好きな犬の場合、うれしょんのリスクはさらに高まります。お客さんにも事情を説明し、協力してもらうことが大切です。
「うちの子、興奮するとおしっこを漏らしてしまうことがあるので、少し落ち着くまでは構わないようにしてもらえますか?」と、事前にお願いしておきましょう。
また、お客さんが来る前に、クレートやサークルで待機させておくのも有効な方法です。インターホンの音で興奮してしまう場合は、音が鳴ったら「ハウス」の指示でクレートに入るようにトレーニングしておくのも良いでしょう。犬が落ち着いてから、リードをつけた状態で対面させると、万が一の時もコントロールしやすくなります。

叱るのは逆効果!正しい対処法
もし愛犬が目の前でうれしょんをしてしまったら、驚いてつい「コラ!」「ダメでしょ!」と大きな声で叱ってしまいたくなるかもしれません。しかし、これは絶対にやってはいけないNG対応です。
うれしょんを叱ってはいけない理由
- 勘違いを招く:犬にとっては「粗相をしたら構ってもらえた」と学習し、気を引くために繰り返す原因になります。
- 恐怖心をあおる:服従心からうれしょんしている場合、叱られることでさらに恐怖を感じ、余計に漏らしてしまうという悪循環に陥ります。
- 信頼関係を損なう:犬の「大好き」という気持ちを否定することになり、飼い主さんへの不信感につながる恐れがあります。
では、どうすれば良いのでしょうか。正解は「無言で、冷静に、事務的に片付ける」です。犬に一切声をかけず、目も合わせず、まるで何もなかったかのように静かに掃除をしてください。この「うれしょんをしても、飼い主さんの関心を引けない」という経験を積ませることが、行動の改善につながります。
オムツやマナーバンドの活用も有効
トレーニングと並行して、物理的な対策を取り入れるのも非常に有効な手段です。特に、どうしても粗相をされたくない場面では、犬用のオムツやマナーバンドが心強い味方になります。
例えば、以下のような状況で活用するのがおすすめです。
- 友人宅やドッグカフェなど、他の方のスペースにお邪魔する時
- 公共交通機関を利用する時
- しつけ教室など、他の犬や人が多く集まる場所へ行く時
オムツやマナーバンドは、うれしょんそのものを治すわけではありません。しかし、万が一の失敗を防ぐことで、飼い主さんの精神的なストレスを大幅に軽減してくれます。飼い主さんが「また漏らしたらどうしよう…」とピリピリしていると、その緊張が犬にも伝わってしまいます。物理的な対策で安心感を得ることも、トレーニングを円滑に進めるための重要なポイントです。
どうしても治らない場合は動物病院へ
これまで紹介したトレーニングや対策を試しても、うれしょんが全く改善されない場合や、興奮していない時にもおしっこを漏らすことがある場合は、何らかの病気が隠れている可能性も考えられます。
特に、以下のような様子が見られる場合は、一度かかりつけの動物病院に相談することをおすすめします。
- おしっこの回数が異常に多い
- おしっこをする時に痛そうに鳴く
- おしっこに血が混じっている
- 水を飲む量が急に増えた
- 元気や食欲がない
これらの症状は、膀胱炎、尿路結石、腎臓病、糖尿病などの泌尿器系や内分泌系の疾患のサインである可能性があります。特にメスは尿道が短く、膀胱炎にかかりやすい傾向があるとされています。
うれしょんだと思っていたものが、実は病気の症状だったというケースもゼロではありません。愛犬の様子に少しでも気になる点があれば、自己判断せずに獣医師の診察を受けましょう。
犬のうれしょんはいつまで?焦らず向き合おう
この記事では、犬のうれしょんがいつまで続くのか、その原因と治し方について詳しく解説しました。最後に、記事の重要なポイントをまとめます。
- 犬のうれしょんの主な原因は「興奮」と「服従心」
- 子犬のうれしょんは膀胱の未発達が原因で成長と共に改善することが多い
- 成犬のうれしょんがいつまで続くかは年齢より個々の性格による
- うれしょんをしやすいのは子犬や小型犬、怖がりな性格の犬
- 治し方の基本は犬を過度に興奮させないこと
- 飼い主が冷静に対応し興奮をあおらないことが重要
- 帰宅時や来客時は犬が落ち着くまで構わないのがコツ
- うれしょんをしても絶対に叱ってはいけない
- 叱ると逆効果になり悪化させる可能性がある
- 正しい対処は無言で冷静に片付けること
- 「粗相をしても注目されない」と犬に学習させる
- お出かけ時にはオムツやマナーバンドの活用が有効
- 飼い主のストレス軽減も改善への近道
- トレーニングしても治らない場合は病気の可能性も考慮する
- 気になる症状があれば動物病院へ相談する
犬のうれしょんは、飼い主さんへの「大好き」という気持ちの表れでもあります。困った行動ではありますが、その裏にある愛犬の健気な気持ちを理解し、焦らず、根気強く向き合っていくことが大切です。この記事が、あなたと愛犬の快適な毎日の一助となれば幸いです。