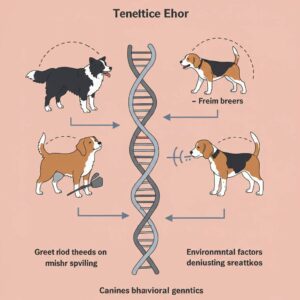愛犬が普段より元気ない様子で寝てばかりいるけれど、ご飯の時間になるとしっかり食べる…そんな姿を見て、「もしかしてどこか悪いのかな?」と不安に感じる飼い主さんは少なくないでしょう。犬が元気ないのに食欲はある状態で寝てばかりいる時、その背景には単なる習性から病気のサインまで、様々な理由が考えられます。この記事では、愛犬のその様子が心配ないものなのか、それとも注意が必要な状態なのかを見極めるためのポイントを、専門的な視点から分かりやすく解説します。
- 犬が寝てばかりいる生理的な理由
- 病気の可能性がある危険なサイン
- 飼い主ができる生活改善のコツ
- 動物病院を受診すべきタイミングの判断基準
犬 元気 ない 食欲 ある 寝 て ばかりなのはなぜ?
- 犬の睡眠時間はもともと長い
- 年齢による睡眠時間の変化
- 季節や気温が睡眠に与える影響
- 運動不足や環境の変化が原因か
- ストレスやうつ症状の可能性
犬の睡眠時間はもともと長い
まず知っておきたいのは、犬は人間よりもずっと長く眠る動物であるということです。犬の睡眠は、浅い眠りである「レム睡眠」の割合が多く、ぐっすり熟睡する時間は短いとされています。そのため、物音ですぐに目を覚ますことができるのです。
この睡眠スタイルは、短い睡眠をこまめに繰り返すことで体力を回復させるためのものです。平均的な成犬の睡眠時間は1日に12時間~15時間ほどにも及び、一日の半分以上を寝て過ごしていることになります。そのため、飼い主さんから見て「寝てばかり」と感じても、犬にとってはごく自然な姿であることがほとんどです。
豆知識:祖先から受け継がれた睡眠スタイル
犬の祖先は群れで生活し、外敵から身を守るために常に警戒を怠らない必要がありました。その「番犬」としての習性が、現代の犬にも受け継がれており、浅い眠りを繰り返すようになったと言われています。
年齢による睡眠時間の変化
犬の睡眠時間は、ライフステージによって大きく変動します。特に子犬とシニア犬(老犬)は、成犬期よりも長い睡眠時間を必要とします。

子犬の場合
子犬は心身ともに成長の真っ最中です。成長には多くのエネルギーが必要なため、1日に18時間から20時間近く眠ることも珍しくありません。遊んだ後に突然電池が切れたように眠ってしまうのは、エネルギーを蓄え、健やかな体を作るために不可欠な時間なのです。食欲が旺盛であれば、基本的には健康な証拠と考えてよいでしょう。
成犬の場合
成犬の睡眠時間は平均で12時間~15時間ほどですが、犬種や個々の性格、生活リズムによって差が出ます。特に、日中に飼い主が留守で刺激の少ない環境にいる犬は、退屈しのぎに寝て過ごす時間が長くなる傾向があります。
シニア犬の場合
7歳頃からシニア期に入ると、犬は再び睡眠時間が長くなります。これは体力の低下や代謝の変化により、回復により多くの時間が必要になるためです。シニア犬は18時間以上眠ることもあり、食事や排泄の時間以外はほとんど寝ているというケースも少なくありません。無理に起こしたりせず、穏やかに過ごせる環境を整えてあげることが大切です。
| 年齢ステージ | 平均睡眠時間(1日あたり) | 特徴 |
|---|---|---|
| 子犬期(~1歳頃) | 18~20時間 | 心身の成長のために多くの睡眠が必要。 |
| 成犬期(1~7歳頃) | 12~15時間 | 活動的だが、睡眠でしっかり体力を回復させる。 |
| シニア期(7歳頃~) | 18~20時間 | 体力の低下に伴い、回復に時間がかかるため睡眠時間が増加。 |
季節や気温が睡眠に与える影響
犬は気温の変化に敏感な動物です。そのため、季節の変わり目や気温の急な変動は、犬の活動量や睡眠時間に影響を与えることがあります。
例えば、夏の暑い日には、人間と同じように夏バテを起こし、体力を消耗しないように日中は涼しい場所でじっと動かずに寝て過ごすことが多くなります。逆に冬の寒い日も、体温を維持するためにエネルギーを温存しようと、活動量が減って眠る時間が増える傾向が見られます。
快適な生活環境を
犬が快適に過ごせるよう、エアコンなどを活用して室温や湿度を適切に管理してあげることが、愛犬の健康維持につながります。特に寒暖差の激しい時期は、体調を崩しやすいため注意が必要です。
運動不足や環境の変化が原因か
病気や加齢といった理由以外にも、日常生活の中に睡眠時間が長くなる原因が隠れていることがあります。それは、運動不足や環境の変化によるストレスです。
毎日の散歩や遊びの時間が不足していると、犬はエネルギーを発散できず、体力を持て余してしまいます。その結果、やることがなくなり、なんとなく寝てばかりいるという状態に陥ることがあります。特に室内飼育の小型犬は運動不足になりがちなので、意識的に遊ぶ時間を作ってあげることが重要です。
環境の変化に注意
犬は環境の変化にデリケートな動物です。引っ越しや家族構成の変化(新しい家族やペットが増える、子供が生まれるなど)、飼い主の生活リズムの変更といった出来事が、犬にとって大きなストレスとなることがあります。ストレスを感じると、不安から活動量が減り、自分の安心できる場所でじっと寝て過ごす時間が増えることがあります。

ストレスやうつ症状の可能性
前述の通り、環境の変化などが原因で強いストレスを感じると、犬も人間のように「うつ」に似た症状を示すことがあります。寝てばかりいることに加えて、これまで好きだった遊びに興味を示さなくなったり、無気力な様子が見られたりする場合は注意が必要です。
食欲はあるものの、どこか表情が乏しく、飼い主とのコミュニケーションを避けるような行動が見られる場合は、何らかの心理的な問題を抱えているサインかもしれません。愛犬のささいな変化を見逃さないよう、日頃からよく観察することが大切です。
愛犬がリラックスして過ごせているか、日々の生活に退屈を感じていないか、今一度振り返ってみましょう。飼い主さんとの楽しいふれあいの時間が、何よりのストレス解消になりますよ。
犬 元気 ない 食欲 ある 寝 て ばかりで見られる病気の兆候
- 見逃してはいけない危険なサイン
- 甲状腺機能低下症など考えられる病気
- 飼い主ができる生活改善のコツ
- 快適な休息スペースを整えよう
- 動物病院を受診するタイミング
見逃してはいけない危険なサイン
「寝てばかりだけど食欲はある」という状態でも、それが病気のサインである可能性はゼロではありません。大切なのは、睡眠時間以外の変化に気づくことです。以下のような症状が合わせて見られる場合は、単なる習性や加齢ではなく、病気が隠れている可能性があります。

こんな症状は要注意!
寝てばかりいることに加え、以下のような変化が見られたら、早めに動物病院を受診しましょう。
- 呼んでも反応が鈍い、または遊びに誘っても乗り気でない
- 急に体重が増えたり、逆に減ったりした
- 水を飲む量や尿の回数が異常に増えた
- 嘔吐や下痢を繰り返す
- 呼吸が荒い、咳をする、ゼーゼーという音がする
- 体を触られるのを嫌がる(関節などに痛みがある可能性)
- 昼夜が逆転したり、夜鳴きがひどくなったりした(特にシニア犬)
これらのサインは、体が発している重要なSOSです。見過ごさずに対応することが、愛犬の健康を守る上で非常に重要になります。
甲状腺機能低下症など考えられる病気
元気がない、寝てばかりといった症状の背景には、様々な病気の可能性が考えられます。ここでは、代表的なものをいくつか紹介します。ただし、これらはあくまで一例であり、自己判断は絶対に避けてください。
甲状腺機能低下症
体の代謝を活発にする甲状腺ホルモンの分泌が低下する病気です。代謝が落ちるため、元気消失、活動量の低下(寝てばかり)、体重増加、脱毛、皮膚のトラブルといった症状が見られます。中~高齢の犬に多く、特に柴犬、ゴールデン・レトリバー、ダックスフンドなどで発症しやすいという報告があります。
クッシング症候群(副腎皮質機能亢進症)
副腎から分泌されるホルモンが過剰になる病気で、これも高齢の犬に多く見られます。症状としては、多飲多尿(水をたくさん飲み、おしっこをたくさんする)、食欲の異常な増加、お腹が膨れる、脱毛、筋肉の衰えなどが特徴です。進行すると糖尿病などを併発するリスクもあります。
糖尿病
血糖値を下げるインスリンの働きが悪くなる病気です。クッシング症候群と同様に多飲多尿や体重減少が見られ、疲れやすくなるため寝ている時間が長くなることがあります。
認知症
シニア犬の場合、脳機能の低下による認知症の可能性も考えられます。ぼんやりしている時間や寝ている時間が長くなるほか、目的もなくうろうろ徘徊する、狭い場所に入り込んで動けなくなる、夜鳴きをするといった症状が典型的です。
飼い主ができる生活改善のコツ
愛犬が病気ではなく、単なる運動不足や退屈から寝てばかりいる場合、生活習慣のちょっとした見直しで活動的になることがあります。ここでは、飼い主さんができる生活改善のポイントをご紹介します。
散歩や遊びの「質」を見直す
毎日の散歩は、ただ歩くだけでなく、犬の五感を刺激する絶好の機会です。いつも同じコースではなく、たまには新しいルートを歩いてみたり、公園の土や草の匂いを心ゆくまで嗅がせてあげたりしましょう。また、知育トイ(おやつを入れて探させるおもちゃ)などを使って、頭を使う遊びを取り入れるのも、退屈を解消するのに非常に効果的です。
食事と健康管理
食事のバランスは、犬の活動量に直結します。年齢や活動量に合った適切なフードを選び、おやつの与えすぎには注意しましょう。肥満は万病のもとであり、体が重くなると動くのが億劫になり、さらに寝てばかり…という悪循環に陥りがちです。定期的に体重をチェックする習慣をつけましょう。
快適な休息スペースを整えよう
活動的に過ごす時間と同じくらい、質の高い休息をとることも犬の健康には不可欠です。愛犬が心からリラックスして休める環境が整っているか、今一度見直してみましょう。
寝床のマットは、硬すぎず柔らかすぎない、体圧を分散できるものが理想です。特にシニア犬の場合は、関節への負担が少ないものを選んであげるとよいでしょう。また、犬が安心して過ごせるように、リビングの隅など、静かで落ち着ける場所に専用のベッドやクレートを設置してあげることが大切です。夏は涼しく、冬は暖かいように、季節に応じて毛布やクールマットを活用し、快適な温度と湿度を保ってあげてください。
安心できる「自分の場所」を
犬にとって、誰にも邪魔されずに安心して休める「自分だけの場所」があることは、心の安定につながります。快適な休息スペースは、質の高い睡眠を促し、日中の活動への活力を養う基盤となるのです。
動物病院を受診するタイミング
愛犬の様子が「いつもと違う」と感じたとき、動物病院へ行くべきか迷うこともあるでしょう。しかし、判断に迷う時こそ、専門家である獣医師に相談するのが最善の選択です。
特に、「見逃してはいけない危険なサイン」で挙げたような症状が一つでも見られる場合や、元気や食欲がない状態が2日以上続くような場合は、ためらわずに受診してください。病気は早期発見・早期治療が何よりも重要です。検査の結果、特に異常がなければ、それはそれで安心材料になります。
「このくらいで病院に行くのは大げさかな?」なんて思わなくて大丈夫ですよ。飼い主さんの「何かおかしい」という直感は、とても大切なサインです。手遅れになる前に、勇気を出して獣医師の診察を受けましょう。
犬 元気 ない 食欲 ある 寝 て ばかりの時の見極め方
- 犬の平均睡眠時間は1日に12時間から15時間程度と人間より長い
- 子犬やシニア犬は体力維持のため18時間以上眠ることも普通
- 犬の睡眠は浅い眠りの割合が多くこまめに休息をとるスタイル
- 夏の暑さや冬の寒さで体力を温存するために睡眠が増えることがある
- 運動不足や刺激の少ない生活が原因で寝てばかりになる場合も
- 引っ越しなどの環境変化がストレスになり活動量が減ることがある
- 食欲があっても元気がない場合は他の症状がないか観察する
- 「水を飲む量」「体重」「呼吸の状態」などの変化は重要なサイン
- 嘔吐や下痢、体を触ると嫌がるなどの症状は病気の可能性がある
- 考えられる病気には甲状腺機能低下症やクッシング症候群などがある
- シニア犬の場合は認知症の可能性も視野に入れる
- 自己判断はせず少しでも異常を感じたら動物病院へ相談する
- 日々の散歩や遊びの質を高めて心と体を刺激することが大切
- 犬が安心して休める快適な寝床を整えてあげることも重要
- 愛犬の普段の様子をよく知っておくことが小さな変化に気づく第一歩