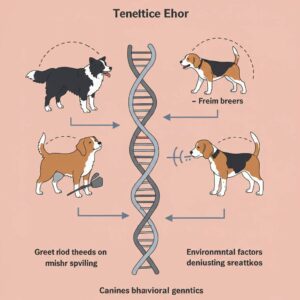愛犬が部屋のマットを夢中になって噛んでいる姿を見て、「どうしてこんな行動をするのだろう?」と疑問に思ったことはありませんか。子犬でも成犬でも見られるこの行動は、単なるいたずらではなく、犬からの何らかのサインかもしれません。この記事では、多くの飼い主さんが気になる犬がマットを噛む理由について、その背景にある習性や心理を掘り下げ、今日からすぐに実践できる具体的な対策まで詳しく解説していきます。愛犬の行動を正しく理解し、より良い関係を築くための一歩にしましょう。
- 犬がマットを噛む習性や心理的な背景
- 子犬と成犬それぞれの噛む理由の違い
- 理由に応じた具体的なやめさせ方やしつけのコツ
- 噛まれにくく安全なマットの選び方
考えられる犬がマットを噛む理由【習性や心理】
- 歯の生え変わりで口の中がむずがゆい
- ストレスが溜まっているサインかもしれない
- 退屈しのぎや遊びの一環として噛む
- 飼い主の気を引きたいという気持ちの表れ
- マットの素材や匂いへの好奇心と探索行動
歯の生え変わりで口の中がむずがゆい

特に子犬によく見られる行動ですが、犬がマットを噛む大きな理由の一つに、歯の生え変わりが挙げられます。生後4ヶ月から半年の間に、子犬は乳歯から永久歯へと生え変わる時期を迎えます。
このとき、人間の子どもと同じように歯茎にむずがゆさや違和感、軽い痛みを覚えることがあります。その不快感を和らげるために、手近にあるものを噛んでしまうのです。中でも、適度な弾力と噛みごたえのあるマットは、子犬にとって格好のターゲットになりやすいと言えるでしょう。
ポイント:噛むのは成長の証
歯の生え変わりによる噛み行動は、犬の成長過程における自然な行動です。そのため、強く叱るのではなく、噛んでも良い代替品を与えて欲求を満たしてあげることが重要になります。
もし、成犬であっても歯をしきりに気にしたり、硬いものを避けるような場合は、歯周病などの口内トラブルの可能性も考えられます。普段から愛犬の口の中をチェックする習慣をつけておくと安心です。
ストレスが溜まっているサインかもしれない
犬は非常に繊細な動物であり、ストレスを感じると問題行動として何かを噛むことがあります。マットを執拗に噛み続ける行動は、愛犬が何らかのストレスを抱えているサインかもしれません。
犬がストレスを感じる原因は様々です。例えば、以下のようなものが挙げられます。
- 運動不足でエネルギーが有り余っている
- 留守番の時間が長く、分離不安を感じている
- 引っ越しや家族構成の変化といった環境の変化
- 飼い主とのコミュニケーション不足
- 雷や工事の音など、特定の騒音に対する恐怖
このように、有り余ったエネルギーを発散させたり、不安や恐怖から逃れるための「転嫁行動」として、身近にあるマットを噛んでしまうのです。もし、以前よりも噛む頻度が増えたり、他に体を舐め続けたり、尻尾を追いかけるといった行動が見られたりする場合は、ストレスを疑ってみる必要があります。
注意:ストレスサインを見逃さない
マットを噛む行動がエスカレートすると、誤飲などの事故につながる危険性もあります。愛犬の様子をよく観察し、ストレスの原因を特定して取り除いてあげることが根本的な解決策となります。
退屈しのぎや遊びの一環として噛む

犬にとって「噛む」という行為は、本能的な欲求の一つであり、遊びの延長線上にある行動です。特にエネルギーレベルの高い犬種や若い犬は、退屈な時間を持て余してしまうと、手近なものを遊び道具にしてしまいます。
マットは、引っ張ったり、振り回したり、噛みちぎったりと、犬にとって魅力的な要素がたくさん詰まっています。飼い主が留守にしている間や、構ってもらえない時間に、退屈を紛らわすための格好のおもちゃとして認識されてしまうのです。
また、過去にマットを噛んだときに飼い主が慌てて駆け寄ってきた経験があると、「マットを噛むと遊んでもらえる」と学習してしまうケースもあります。これは犬にとっては、飼い主とのコミュニケーションの一環になっている可能性も示唆しています。
「うちの子、私が忙しくしてると決まってマットをカミカミし始めるのよね…」なんて経験はありませんか?もしかしたら、それは「ねぇ、こっちを見て!遊んで!」という愛犬からの可愛いアピールなのかもしれませんね。
飼い主の気を引きたいという気持ちの表れ
犬は非常に社会性が高く、飼い主とのコミュニケーションを求める動物です。そのため、飼い主の注意を引くために、わざといたずらをすることがあります。マットを噛む行動も、その一つとして考えられます。
例えば、犬がマットを噛み始めたときに、飼い主が「ダメ!」「こら!」と大きな声を出したり、駆け寄ってきたりすると、犬は「マットを噛むと飼い主さんが注目してくれる」と学習してしまうことがあります。たとえそれが叱られるというネガティブな注目であっても、完全に無視されるよりは良いと判断するのです。
この行動は、特に飼い主との触れ合いの時間が不足していると感じている犬に見られがちです。日頃から十分に遊んであげているつもりでも、犬にとってはまだ物足りないのかもしれません。要求吠えや他のいたずらと同様に、注意を引くための行動がマットへの攻撃という形で現れているのです。
マットの素材や匂いへの好奇心と探索行動
犬は優れた嗅覚と好奇心を持っています。新しいマットや、特定の素材・匂いがするマットに対して、「これは何だろう?」という純粋な好奇心から噛んでしまうことがあります。
犬は口を使って物の感触や味を確かめる習性があるため、噛むことは彼らにとって重要な探索行動の一部です。特に、以下のような特徴を持つマットは、犬の興味を引きやすい傾向があります。
- ウールやコットンなど、自然素材の匂いがするもの
- フワフワ、ボコボコといった面白い感触のもの
- 飼い主や家族の匂いが強く染み付いているもの
飼い主の匂いがするマットを噛むのは、安心感を求めている行動とも考えられます。しかし、探索行動がエスカレートして破壊行動につながる前に、その好奇心を別のもので満たしてあげることが大切です。単に「いたずら」と片付けるのではなく、犬の本能的な行動として理解することが求められます。
豆知識:ピカ(異食症)の可能性
食べ物ではないものを執拗に食べてしまう場合は、「ピカ」と呼ばれる異食症の可能性もゼロではありません。栄養不足や精神的な問題が背景にあることも考えられるため、あまりにも行動が異常な場合は、一度獣医師に相談することをおすすめします。
やめさせるには?犬がマットを噛む理由別の対処法
- 十分な運動でエネルギーを発散させる
- 不安や恐怖を感じさせない環境づくり
- 噛んでも良いおもちゃを代わりに与える
- 噛んではいけないことを根気強く教える
- 噛まれにくい素材のマットに交換する
十分な運動でエネルギーを発散させる

マットを噛む理由が運動不足によるストレスや退屈である場合、最も効果的な対処法は十分なエネルギー発散の機会を提供することです。犬が必要とする運動量は、犬種、年齢、個々の性格によって大きく異なりますが、日々の散歩だけでは足りていない可能性があります。
具体的なエネルギー発散方法

- 散歩の質を高める:単に歩くだけでなく、コースを変えたり、早歩きや軽いジョギングを取り入れたりして刺激を与えましょう。
- ドッグランの活用:他の犬と交流したり、思い切り走り回ったりすることは、身体的だけでなく精神的な満足感にも繋がります。
- 室内での遊び:天候が悪い日でも、「持ってきて」遊びや知育トイを使って頭と体を使わせることで、エネルギーを効果的に消費させることができます。
心身ともに満たされることで、問題行動は自然と減少していく傾向にあります。愛犬が満足しているか、その日の活動量を見直してみましょう。
不安や恐怖を感じさせない環境づくり
留守番時の分離不安や、特定の音への恐怖が原因でマットを噛んでいる場合、犬が安心して過ごせる環境を整えることが非常に重要です。
まず、留守番に対しては、短い時間から慣れさせ、飼い主が必ず帰ってくることを学習させましょう。出かける際に大げさに声をかけたりせず、帰宅時もすぐに構うのではなく、少し落ち着いてから接することで、飼い主の不在を特別なことだと認識させないようにします。
また、雷や工事の音など、特定の音を怖がる場合は、以下のような対策が有効です。
安心できる環境づくりのポイント
- 安全な逃げ場所の提供:クレートやケージを布で覆い、犬が隠れられる安心な「巣」を用意してあげる。
- 音のマスキング:テレビやラジオをつけっぱなしにして、外の音を聞こえにくくする。
- 飼い主の冷静な態度:飼い主がパニックになると犬の不安を煽ってしまいます。飼い主は常に落ち着いて、頼れるリーダーとして振る舞うことが大切です。
このように、犬が不安を感じる要因を減らし、リラックスできる空間を提供してあげることで、不安からくる噛み行動を抑制できます。
噛んでも良いおもちゃを代わりに与える
歯の生え変わりや遊びたい欲求など、犬の「噛みたい」という本能的な欲求を無理にやめさせることは困難です。そこで有効なのが、マットの代わりに噛んでも良いおもちゃを与えるという方法です。
犬がマットを噛み始めたら、大きな声で叱るのではなく、静かにおもちゃと交換します。そして、おもちゃを噛んで遊んでいたら、「えらいね!」「上手だね!」とたくさん褒めてあげましょう。これにより、犬は「マットではなく、このおもちゃを噛むと褒められる」と学習していきます。
おもちゃ選びのポイント
| おもちゃの種類 | 特徴とおすすめの犬 |
|---|---|
| デンタルトイ | 歯の生え変わりで歯茎がむずがゆい子犬や、歯垢除去をしたい成犬におすすめ。様々な硬さや形状があります。 |
| 知育トイ | おやつを隠せるタイプのおもちゃ。頭を使いながら遊べるため、退屈しのぎやストレス解消に最適です。 |
| ラバートイ | 丈夫で弾力があり、噛む力が強い犬にも対応できます。不規則なバウンドをするものもあり、犬の興味を引きつけます。 |
愛犬の好みや噛む力に合わせて、複数のおもちゃを用意し、飽きさせない工夫をすることも大切です。
噛んではいけないことを根気強く教える

すべての対策の基本となるのが、「マットを噛むことはいけないこと」だと一貫した態度で教えるしつけです。これには根気が必要ですが、愛犬との信頼関係を築く上で欠かせません。
犬がマットを噛んでいるのを見つけたら、低い声で「いけない」「ノー」など、短い言葉で注意します。このとき、感情的に怒鳴ったり、叩いたりするのは絶対にやめましょう。犬を怯えさせるだけで、なぜ叱られているのかを理解できません。
注意した後は、先述の通り、噛んでも良いおもちゃを与えて正しい行動に誘導し、できたら褒める、という流れを徹底します。家族全員が同じルールで対応することも非常に重要です。人によって対応が違うと、犬は混乱してしまいます。
しつけの注意点:現行犯が原則
犬を叱るのは、必ず「現行犯」のときだけにしてください。時間が経ってから叱っても、犬は何に対して叱られているのか理解できず、飼い主に対する不信感を抱くだけになってしまいます。
噛まれにくい素材のマットに交換する
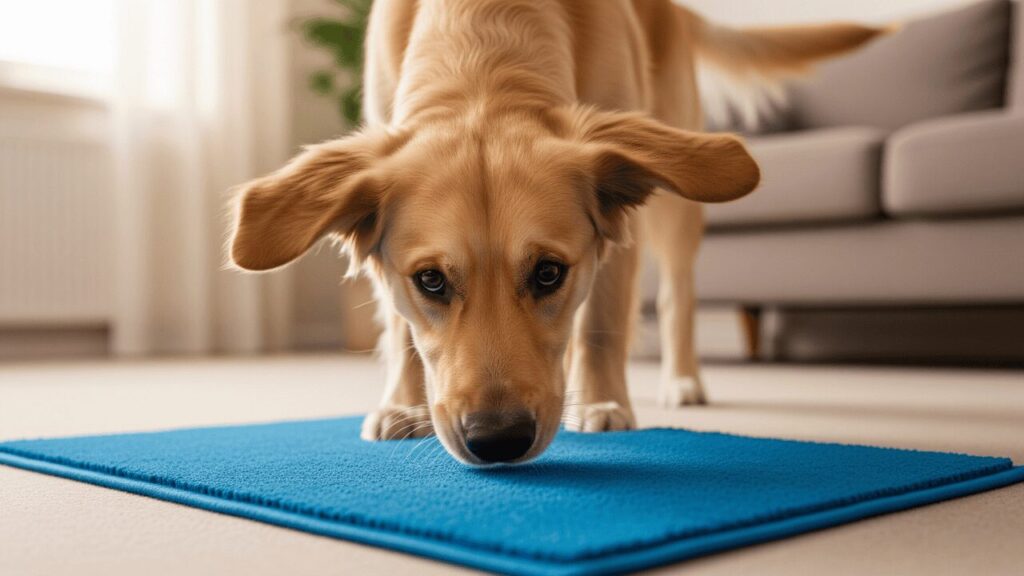
様々な対策を試しても噛み癖が直らない場合や、誤飲のリスクを根本的に減らしたい場合には、物理的に噛まれにくい、あるいは噛んでも壊れにくいマットに交換するというのも一つの有効な手段です。
犬が噛みにくい、あるいは興味を示しにくいマットには以下のような特徴があります。
- 高密度で短い毛足のもの:毛足が長いシャギーラグなどは、引っ張りやすく噛む楽しさを助長します。毛足が短く、目の詰まったものを選びましょう。
- 丈夫な素材のもの:帆布(キャンバス)生地や、アウトドア用品に使われるような丈夫な素材のマットも選択肢になります。
- 滑り止めがしっかりしているもの:マットがズレにくいと、犬が端をくわえて振り回すといった遊びができなくなります。
最近では、ペット用に開発された、爪が引っかかりにくく、耐久性の高いマットも市販されています。初期投資はかかりますが、マットを何度も買い替えるコストや、誤飲による動物病院代を考えれば、結果的に安く済むケースも少なくありません。
思い切ってペット用の丈夫なマットに変えてみたら、愛犬も諦めたのか全然噛まなくなって、お掃除も楽になりました!なんて声もよく聞きます。愛犬の安全と快適な暮らしのための投資と考えてみるのも良いかもしれませんね。
様々な犬がマットを噛む理由と対策のまとめ
この記事では、犬がマットを噛んでしまう様々な理由と、それに対する具体的な対処法について詳しく解説しました。最後に、記事全体の要点をリスト形式で振り返ります。
- 犬がマットを噛むのは単なるいたずらではない
- 子犬の場合は歯の生え変わりが主な原因
- 成犬の場合はストレスや退屈が背景にあることが多い
- 運動不足は問題行動の大きな引き金になる
- 留守番時の分離不安も噛む行動に繋がる
- 飼い主の気を引くためにわざと噛むこともある
- マットの素材や匂いへの好奇心も理由の一つ
- 対策の基本はエネルギーを発散させること
- 犬が安心して過ごせる環境づくりが重要
- マットの代わりに噛んでも良いおもちゃを与える
- おもちゃで遊べたらしっかり褒めて学習させる
- 「いけない」としつける際は一貫した態度を保つ
- 叱るときは感情的にならず現行犯で行う
- 物理的に噛まれにくいマットに交換するのも有効な手段
- 行動が異常な場合は獣医師への相談も検討する